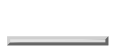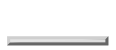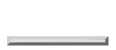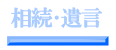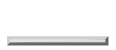遺留分について
遺産の一定割合は相続人のために確保されています
自分の遺産(相続財産)を、誰にどのように配分するかは、生前に遺言書を書いておくことによって、ある程度遺言者の決めることができます。
遺言では、各相続人の相続分を法定相続分と異なる割合に定めたり、相続人でない第三者に遺産の全部または一部を承継させる(遺贈する)ことも可能です。
遺言が残っていた場合、法定相続分よりも遺言の方が優先されますので、たとえ法定相続分を有する相続人であっても、必ずしも遺産を承継することができるとは限らないことになります。
場合によっては第一順位の相続人(子や配偶者)であっても、相続分が全くなかったり、非常に少なくなることもあります。
ただし、遺言によって遺産の分配方法を自由に決められるといっても、残された家族の生活も保障してあげる必要がありますし、亡くなった方の財産が貯まるまでには家族の寄与もあったと考えられ、その分はきちんと精算しなければなりません。
そこで、さすがに近親者に1円も残さないというのは酷だろうと考えられるため、遺産のうちの一定の割合が、近親の相続人の権利として確保されています。
この相続人に確保されている一定の割合のことを「遺留分」といいます。
遺留分権利者
遺留分を有する「遺留分権利者」は、兄弟姉妹以外の相続人です。
つまり、子(いないときはその代襲相続人である孫やひ孫)や配偶者、直系尊属が相続人になるときはその直系尊属が遺留分権利者となっています。
注意しなければならないのは、兄弟姉妹は、第三順位の相続人だけど遺留分はないということです。
したがって、兄弟相続が発生するの場合(子や孫がおらず、直系尊属もいない場合)に、遺言が残っていた場合は、遺言の内容にかかわらず誰の遺留分も侵害しませんので、基本的にはその遺言書の内容どおりに遺産が承継されるということです。
遺留分の割合は、
相続人が直系尊属のみである場合・・・遺産の3分の1
それ以外の場合・・・遺産の2分の1
となっていますので、この限度で相続人たちに権利が確保されています。
そして、遺留分権利者である各相続人は、この遺留分の中で、それぞれの法定相続分に応じて権利(具体的遺留分)を有しています。
例えば、遺産が300万円の場合の遺留分は次のようになります。
(例1)相続人が配偶者と2人の子である場合
この場合、遺留分全体(抽象的遺留分)は遺産の2分の1なので、150万円です。
配偶者はその2分の1なので75万円、子は残りの2分の1を等分するので37万5000円ずつを、遺留分として確保することができます。
ここでもし、「200万円を長男の嫁に遺贈する」というような遺言があれば、100万円しか残らないので、50万円分の遺留分を侵害していることになります。
(例2)相続人が配偶者と両親である場合
遺留分全体は同じく150万円ですが、法定相続分の割合は配偶者:直系尊属=2:1なので、配偶者の遺留分は100万円、両親の遺留分はそれぞれ25万円ずつです。
両親の片方が既に亡くなっていたら、配偶者が100万円で、生存する親が50万円です。
(例3)配偶者がおらず、相続人が両親だけの場合
遺留分としては遺産の3分の1なので100万円、それを両親が等分して50万円ずつの遺留分を有することになります。
生存している親が1人だけなら、その人が100万円です。
遺留分を侵害する遺言の効力
どのような遺言の内容であったとしても、遺留分については、侵害することができないものとされています。
ただし、遺留分を侵害するような遺言であっても、遺言自体は有効です。
あくまでも遺留分権利者は、「遺留分を侵害した分を返せ」と請求する権利を有するにすぎません。
遺留分を侵害している者に対して「返せ」という権利を「遺留分侵害額請求権」といい、遺留分侵害された額に相当する金銭の支払いを請求することができます。
請求する相手方(遺留分を侵害している者)は、遺言者ではなくて、遺言によって利益を得た人です。
例えば、「長男○○に全財産を相続させる」という遺言であったとすれば、その長男に対して請求します。
遺留分侵害額請求の方法は特に決まっていませんので、口頭でも構いませんが、証拠を残しておくために、内容証明郵便等で請求することが確実です。
逆に言えば、遺留分権利者が遺留分侵害額請求をしなければ、遺言の内容どおりに遺産を承継することができるということです。
とはいえ、争いの元にもなりかねませんので、遺留分侵害額請求がされることが予想されるような場合であれば、遺言者は遺言作成の段階で、遺留分については考慮した内容の遺言にしておいたほうがよいこともあります。
なお、民法(相続法)改正の施行日2019年7月1日より前に発生した相続に関しては、遺留分侵害に対して遺留分侵害額請求ではなく「遺留分減殺請求」をすることができます。
これは、金銭請求ではなく、遺留分について取り戻す(例えば不動産の贈与が遺留分を侵害している場合、遺留分相当の持分を遺留分権利者に移転させる)権利でしたが、権利関係が複雑になることから、この制度は廃止されることになりました。
遺留分の算定方法
遺留分を算定するうえでの「被相続人の財産」は、必ずしも相続時の財産とは一致しません。
- 相続開始時の財産
- 1年以内に贈与した財産
- 1年より前に遺留分を侵害することを知って贈与した財産
の総額から債務額を控除した額が基準となり、これの2分の1なり3分の1が遺留分となります
なお、改正民法施行後の相続については、相続人に対する贈与(特別受益に当たるような贈与)の場合は、1年ではなく10年以内のものが対象となります。
請求する順序も、まずは遺贈、その次に最新の贈与、その次にその前の贈与・・・という具合に決まっています。
遺留分侵害額請求の期間制限
このように、遺言者の意思にかかわらず、絶対的に守られる相続人の権利である遺留分ですが、請求をしなければ実現されません。
そして、受遺者の地位を安定させるため、遺留分侵害額請求ができるのは、遺留分権利者が「相続の開始及び遺留分を侵害する贈与又は遺贈があったことを知った時」から1年以内です。
また、遺留分の侵害があったことを知らなくても、相続開始の時から10年が経過すれば、やはり遺留分額侵害請求はできなくなります。
そのため、遺留分侵害額請求の有効性について、請求をした時期で争いが生じることがありますので、内容証明郵便等の証拠が残る方法で請求することが望ましいでしょう。
遺留分があるからといって安心できませんので、遺留分が侵害されていることを知ったときは、すみやかに請求をしましょう。
相続に関するご相談
遺留分を侵害された遺贈が出てきた場合や、遺留分で揉めない遺言書の作成についてのご相談は、お気軽に当事務所までお問い合わせください